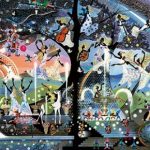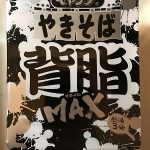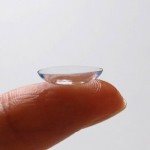最近、4Kディスプレイを使用して高グラフィックの3Dオンラインゲームをいじくり始めているのですが、7年前に自作したメインパソコンだと流石に4Kの解像度でプレイしているとやや描画が追いつかない状況もありますね。
ビデオカードのアップグレードやHDDやらSSDへの換装、メモリの増設はそれなりにやってはいますが、流石に7年前のパソコンだと最新のゲームを最高のグラフィックレベルでプレイする事は出来ないようです。
別にそこまでゲームに固執する訳でもないのですが、久しぶりにパソコンを自作してみたくなったので2017年中には出来る限りハイエンドなゲーミングパソコンを自作する事を目標にして、最近の情勢を踏まえて一から全てのパーツのスペックや価格などについて調べてみました。
因みにドスパラなどのBTO(ある程度パーツを選んでカスタマイズ可能)でゲーミングパソコンを買うのと自作の場合とでどちらが安くなるかという議論がありますが、このような議論は論点がずれがちで、自作の方が高くなるという意見もあります。
もちろん、自作でパーツに拘って良い物を選びすぎると滅茶苦茶高くもなりますし、廉価な大量生産が前提のパソコンであればBTOの方が安くなる場合もあるでしょう。
ただし、この場合は前提がゲーミングパソコンですので、廉価モデルのパーツ程大量に仕入れ・販売が出来ませんので同じようなスペックのものであれば10~15%くらいは安くなる傾向にあるようです。
例えば2017年1月の段階では代表的なBTOパソコンと同等のものを自作した場合、コストの差は以下のようになります。
BTOと自作パソコンのコストの比較
代表的な大手のBTOパソコンメーカーの「ドスパラ」「マウスコンピュータ」「パソコン工房」のハイエンドパソコンのスペックと価格は以下の通りとなっています。
| ドスパラ | ドスパラ | マウス | パソコン工房 |
|---|---|---|---|
| ブランド | ガリレア | G-Tune | LEVEL∞ |
| 参考価格 | 237,578円 | 226,584円 | 191,384円 |
| 最新価格 | |||
| CPU | Corei7-7700K | Corei7-7700 | |
| グラボ | GTX1080 | ||
| DDR4メモリ | PC-4-19200 8GB*2 | 4GB*2 | |
| SSD | 525GB | 480GB | 240GB |
| HDD | 3TB | 1TB | |
| 光学 | DVDドライブ | ||
| マザー | Z270 ATX | ||
| 電源 | 800W | 700W | 500W |
| ケース | ミドルタワー | ||
| OS | Win10 Home 64bit DSP版 | ||
因みにほぼ同等のスペックでパソコンを自作した場合、上の表のドスパラのモデルを基準に考えると2017年1月現在では21万円弱になります。
| 自作PC | Amazon | |
|---|---|---|
| CPU | Corei7-7700K | 46,500円 |
| CPUクーラー | 12cm | 3,100円 |
| グラボ | GTX1080 | 77,700円 |
| DDR4メモリ | PC-4-19200 8GB*2 | 8,500円 |
| SSD | 525GB | 14,000円 |
| HDD | 3TB | 9,500円 |
| 光学 | DVDドライブ | 1,800円 |
| マザー | Z270 ATX | 18,000円 |
| 電源 | 800W | 11,500円 |
| ケース | ミドルタワー | 6,000円 |
| OS | Win10 Home 64bit DSP版 | 12,700円 |
| 計 | 209,300円 |
|
このケースでは大体12%、金額にすると3万円くらいは安くなります。
とは言え、パソコンを自作するには各種パーツの下調べが必要ですし、動かなくても何の保証もありませんので、どちらが得かは一概には言えません。
BTOと比較した場合の自作パソコンのメリットは以下の通りとなりますので、目的に合わせてBTOか自作かを考えれば良いでしょう。
自作パソコンのメリットとデメリット
まずは自作パソコンのメリットから説明します。
メリット
- パソコンを自作する事でハードウェアの知識が増えて以後のカスタマイズの幅が広がる
- パソコンが壊れた時にもどのパーツが悪いか察しがつくようになるので自分で修理が可能
- 各種パーツを全てのメーカーから選ぶ事が出来る
- コストが10~15%程度安くなる
デメリット
- 下調べをするのにかなり時間が掛かる
- いざパソコンを組み上げてもパーツを選び間違えたり、初期不良のパーツがあると原因切り分けが面倒
- 壊れた場合には100%自己責任で自分で修理しなければならない
結論としては、自作パソコンのメリットはそれに掛かる時間を考え合わせるとコストの面では微妙です。
ハードウェアに興味がなく、面倒な事が嫌いな人であれば自作パソコンにはあまりメリットがありませんのでBTOをおすすめしますが、趣味の範疇で調べる事が好きであったり、今後も自分で色々カスタマイズする可能性があるのならば一度自作パソコンを組んでみる事をおすすめします。
私の場合には断然自作派ですので、今回のパソコン自作計画に当たりついでと言う訳でもないのですがこれからパソコンを自作しようと思っている自作初心者の方向けに、このページさえ読めばパソコンが自作出来るようにマニュアルを作ります。
始めに押さえておきたい自作パソコンを組むために必要なパーツ
ここでは自作パソコンを組む為に必要なパーツ一式とそれぞれの役割についてざっくりと解説します。
パーツ類をざっと列挙すると以下の通りとなります。
- CPU(Central Processing Unit)
パソコンの頭脳とも言うべきパーツで、プログラムなどを読み込んで演算を行い、命令を実行します。 - メモリ
CPUが実行するプログラムをHDDやSSDから吸い出して一時的に記憶・展開する作業スペースのようなものです。 - ビデオカード(グラフィックボード)
GPU(Graphics Processing Unit)とも呼ばれ、主に3D(三次元)のコンピューターグラフィックをディスプレイに描画し、出力する為のパーツで、3D描画の為の演算処理を行う頭脳を搭載しています。CPUと同様にカード内にメモリを搭載し、メモリ上で命令を実行する作業を行います。 - 記憶装置
HDD・SSDなどがこれに当たりますが、OSやアプリケーションなどの永続的に保存しておく場所です。CPUはここからメモリ上に展開されたプログラムを実行します。 - 光学ドライブ
こちらも記憶装置の一種ですが、DVDやCDなどの円盤状のメディアに情報の読み書きを行います。 - マザーボード
各パーツの土台となる基盤で、パーツごとのバイパスの役割を果たします。CPUやビデオカードなどの種類によっては適合しないケースもあります。 - 電源ユニット
パソコンに電気を供給するユニットです。モデルにより供給できるワット数が決まっており、パソコンに使用されている各パーツの使用電力以上の供給能力が必要です。 - ケース
マザーボードや各パーツを収納する箱です。省スペースなものが邪魔にならずに良いですが、冷却性能やカスタマイズの事を考えると大きいケースの方が楽です。 - ケースファン
パソコンの各部品は熱に弱いので、パソコンのケース内に外から風を取り込んだり、外に熱気を放出したりする事で直接・間接的にパーツを冷却します - CPUクーラー
CPUから熱を吸収する放熱板を備えており、ファンで放熱板に風を当てる事で間接的にCPUを冷却します。CPUと同梱のもの、別売のものがあります。 - グリス
CPUとCPUファンの間に塗り、隙間を無くす事でCPUからファンの放熱板に熱の伝達効率を上げ、CPUの冷却を助けます。
パーツを選ぶ上でのポイント
次に上の項目で挙げた各パーツを選ぶ上でのポイントについて説明します。
原則としてはパソコンの頭脳に当たるCPUの性能アップに伴い、その性能を100%引き出す為にマザーボートやメモリなどの各種パーツもマイナーチェンジ・フルモデルチェンジを行っています。
従って、CPUがフルモデルチェンジを遂げてしまうとマザーボードやメモリなどは古いものは使えなくなって行く傾向にあります。
そう言った点を踏まえながら、各パーツのスペックの見方や選ぶポイントなどについて解説します。
CPUはソケットの種類や対応メモリに注意
CPUは世代により、マザーボードに挿し込むソケットの形が異なる場合があります。
例えば、デスクトップ用のCPUであればインテルの「Core i7-7700系」が2017年初頭の最新モデルになりますが、このCPUは「Core i 7」第7世代と呼ばれ、ソケットの種類が「LGA1151(別名Socket H4」という規格を採用しています。
2世代前のインテルのCPUに採用されていた「LGA1150」とはピンの数が違うために互換性はなく、対応するマザーボードは全く別物となります。
メモリに関してはも一世代前のインテルのCPUに対応する規格の「DDR3」は、最新のCPUでは一部使用出来るものもありますが、完全対応しているのは「DDR3」からフルモデルチェンジしたメモリ規格の「DDR4」のみとなります。
つまり選ぶCPUによって、マザーボードとメモリはある程度新しい物を選ばなけれなならないという事です。
では、これからゲーミングパソコンを自作する前提で選択肢とるCPUの性能面についてみて行きましょう。
現状考え得るCPUの選択肢は、インテルのCPUは第6世代の「Core i 7-6700系」、第7世代の「Core i 7-7700系」となっていますが、デスクトップ向けのハイエンドの現行品で、ゲーミングパソコン向けのCPUは「Core i7-6700」「Core i7-6700K」「Core i7-7700」「Core i7-7700K」の4つとなります。
※2世代前の第5世代のCPUには更に高性能なCPUもありますが、ソケットの形状が型落ちになりますので今後のパーツのバージョンアップの事を考えると避けた方が良いと思います。
| インテル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型番 | Core i7-7700K | Core i7-7700 | Core i7-6700K | Core i7-6700 |
| コア数 | 4コア | |||
| スレッド数 | 8スレッド | |||
| クロック周波数 | 4.2GHz~4.5GHz | 3.6GHz~4.2GHz | 4.0GHz~4.2GHz | 3.4GHz~4.0GHz |
| キャッシュ | 8MB | |||
| 消費電力/TDP | 91W | 65W | 91W | 65W |
ソケットの規格とメモリについては再度マザーボードの項目で説明しますので、ここではその他の項目を中心に説明します。
コア数とスレッド数の関係
「コア」とは人間の頭の脳味噌に当たる部分で、実際に命令を処理する役割を果たしています。
昔のCPUにはコアは1つしかありませんでしたが、2006年以降は複数のコアを持つCPUが登場し、現在では2コア、4コアがスタンダードとなりました。
人間に例えると1人でデスクワークを行うよりも2人で行った方が処理が早くなるのと同様で、他の条件が同じであればコア数が多ければ多い程CPUが行える処理は早くなります。
「スレッド」と言うのは一度に実行出来る命令の一連の流れの事です。
例えば処理1から始まり、処理10まで続く命令があった場合、この命令の流れをスレッドと呼びます。
上で紹介したインテルのCPUは4コア・4スレッドとなっていますので、1つのコアが一つのスレッドを実行出来るという事を表しています。
この場合、同じ条件で1コアのCPUとの処理速度を比較すると、処理待ちの負担も軽減されてCPUの負担が減る為、4コアの方は4倍以上のスピードで処理をこなす事が出来ます。
クロック数とはデータ送受信の頻度
CPUは高速で信号の送受信をしながら命令を実行しますが、クロック周波数はこの命令の頻度を表しています。
単位はHz(ヘルツ)で1秒間に1回の信号をやりとりするのが1Hzとなります。
最近のCPUではGHzという単位になっていますが、4.0GHzである場合これは1秒間に4ギガ回(4億回)の信号の送受信を行っているという事になります。
1分に1回とか4回の命令実行であれば体感的に多い方が速そうに感じますが、1億回とかの話になると感覚的には分かりにくいと思います。
とりあえず他の条件が同じであればクロック周波数が高い程、処理が速いと覚えておけば大丈夫です。
因みに3.4GHz~4.0GHzという表記は、通常時は3.4GHで稼働しつつ、処理が多くなってくると4.0GHzに送受信頻度を上げるという事です。
キャッシュは超高速なデータ記憶装置
先程CPUはHDDやSDDからメモリ上に展開された情報とやり取りを行い、命令の送受信を行うと説明しましたが、CPUの性能の向上にメモリが追いついておらず、メモリの限界速度によってパソコン全体の処理が遅くなるのを防ぐ為に、CPUには「キャッシュ」という超高速でデータの読み書きが可能な記憶装置が内蔵されています。
このキャッシュも多ければ多いほど、CPUの処理が早くなります。
TDPはCPUが発する熱量と消費電力
TDPはCPUが冷却が必要な熱の量で、この数値が大きい程能力の高いCPUクーラーが必要になります。
通常の場合にはCPUとセットになっていますが、「Core i7-7700K」「Core i7-6700K」についてはTDPが91Wと大きい為、CPUにクーラーは付属せずに別途購入する必要があります。
また、TDPについては各メーカーとも消費電量と同等と公表しています。
最近のCPUは高性能でも消費電力は控えめになって来ていますが、電源ユニットの容量を決める際には全てのパーツの電力を上回るものを選ぶ必要がありますので、参考として目当てのCPUの消費電力を押さえておきましょう。
ゲーミングパソコン向けのCPUのスペック比較
パソコン業界のCPUのシェアは、現在ではインテルが80%となっており、1強の状態となっています。
かつてのライバルとしては、インテルよりも低価格で同等の性能を持つCPUを開発しているAMDという会社があいりますが、最近の情勢としては3Dベンチマークテストの結果が振るわず、急速にシェアを落としています。
従って何台も自作パソコンを作っているなら別ですが、自作初心者に近いようであれば販売数が多い故に、ネットでトラブルなどの各種情報が出回っているインテル製品を選んだ方が無難でしょう。
インテルのゲーミングパソコン向けのCPUは先程紹介した4モデルになります。
| インテル | |||
|---|---|---|---|
| Core i7-7700K | Core i7-7700 | Core i7-6700K | Core i7-6700 |
| 参考価格 | |||
| 46,880円 | 41,774円 | 35,180円 | 33,800円 |
| 4コア | |||
| 8スレッド | |||
| 4.2GHz~4.5GHz | 3.6GHz~4.2GHz | 4.0GHz~4.2GHz | 3.4GHz~4.0GHz |
| 8MB | |||
| TDP 91W | TDP 65W | TDP 91W | TDP 65W |
| CPUクーラーなし | - | CPUクーラーなし | - |
性能的には「Core i7-7700K」がナンバーワンですが、本体価格以外の面でもデメリットがあります。
これは先程も述べた通り「Core i7-6700K」も同様なのですが、CPUクーラーを別途手配しなければならない点です。
従って価格とコストのバランスを考えれば「Core i7-7700」「Core i7-6700」辺りが現実的な選択となると思います。
因みにBTOで販売されているゲーミングパソコンの人気上位モデルはほとんどがこれらの4つのCPUが使用されています。
どうしても最高の性能を求めるというのであれば、3000円程度でこれらのCPUに対応した評判の良いCPUクーラーがあります。
サイズ 【HASWELL対応】 虎徹 12cmサイドフロー SCKTT-1000
Amazonのレビューを見る限り「Core i7-6700K」に使用しても温度は安定しているようです。
メモリはDDR4の一択
最新のCPUは現状最高速の転送速度を持つ「DDR4」規格のメモリに対応していますので、今からゲーミングパソコンの自作を行うならメモリは「DDR4」を選んだ方が後々まで使えますし後悔もしないでしょう。
メモリは何G積めばいい?
メモリはCPUが実行するプログラムをHDDやSSDから吸い出して一時的に記憶・展開する作業スペースのようなものですので、原則的には多い方が処理速度は上がりますが、他のパーツの限界能力もありますので多すぎても無用の長物になる恐れもあります。
ゲーミングパソコンであれば理想は16G以上ですが、後々増設などを考えるのあればとりあえず8Gで試してみて物足りなければ増設すれば良いと思います。
BTOではゲーミングパソコンのハイエンドモデルで16G、ミドルスペックで8Gとなっています。
ただし、最近はDDR4メモリの価格も下がっており、ものによっては16GBでも7~8千円で買えてしまします。
後で買い足すとトータルではコストがかさみますので、最初に一気に16Gを選択しても良いかも知れません。
メモリにもCPUと同じく動作クロックがある
メモリにもCPUによって動作クロックや転送速度に差があります。
DDR4の場合は以下の通りです。
| モジュール規格 | メモリチップ規格 | チップ最大クロック | 転送速度 |
|---|---|---|---|
| PC4-12800 | DDR4-1600 | 1600MHz | 12.8GB/秒 |
| PC4-14900 | DDR4-1866 | 1866MHz | 14.8GB/秒 |
| PC4-17000 | DDR4-2133 | 2133MHz | 17.0GB/秒 |
| PC4-19200 | DDR4-2400 | 2400MHz | 19.2GB/秒 |
| PC4-21333 | DDR4-2666 | 2666MHz | 21.3GB/秒 |
| PC4-25600 | DDR4-3200 | 3200MHz | 25.6GB/秒 |
| PC4-34100 | DDR4-4266 | 4266MHz | 34.1GB/秒 |
このうち、インテル第6世代のCPU(6700系)に対応しているのは、「DDR4-1866」「DDR4-2133」の2種類のみです。
第7世代の7700系については「DDR4-2400」のみとなります。
※正確にはDDR3Lという「DDR3」のマイナーチェンジ版のメモリも使えますが、あまりメリットがないので「DDR4」一択と考えても良いでしょう。
それ以上の性能のメモリでも動くケースもあるようですが、結局は標準対応までの速度でしか動かないので、安定性を考えた場合、標準対応のメモリを選んだ方が良いでしょう。
転送速度はメモリチップの最大クロックに左右されますので、6700系であれば「DDR4-2133」、7700系ならDDR4-2400」を使用した方が限界性能が高くなる傾向があります。
メモリのクロックはマザーボードのFSB(動作クロック)に合わせる必要がありますが、intel Core i 7-6700などの「LGA1151」ソケットのCPUが使えるマザーボードであれば1866MHz、2133MHz、2400MHzに対応している筈です。
メモリを選ぶ上で注意するポイント
メモリは同じ規格、種類のものであってもメーカーや型番、生産ロットによって動作の安定性が変わるケースがあります。
この辺りは安物でも問題なく使える場合もありますので実際に使用してみなければ分からないのですが、有名ブランドの物であれば価格がやや高めになりますが安定性は高いようです。
BTOサイトのおすすめメモリーや、BTOサイトで販売されているゲーミングパソコンに積まれているメモリを参考にするのが無難かと思いますが、価格重視で選んで容量を増やすのもアリだと思います。
その辺りは考え方次第ですので、自分が良かれと思う方法を選択するのが一番でしょう。
安いメモリはAmazonなどのレビューが参考になると思います。
一応ここではBTOサイトのおすすめの物や、Amazonなどの通販サイトで人気のあるものを紹介します。
》》》ドスパラおすすめ CFD Panram W4U2133PS-8G (DDR4 PC4-17000 8GBx2)![]()
》》》ドスパラおすすめ Panram W4U2400PS-8G (DDR4 PC4-19200 8GB 2枚組)
》》》Amazonで高評価 Crucial PC4-17000 DDR4
》》》Amazonで高評価 Crucial PC4-19200 DDR4
Amazonで販売されているCrucialのメモリは16GBで8千円台ですのでかなりリーズナブルで安定化もありそうです。
メモリのウンチク
この項目は自作PCの為に必ずしも必要な知識ではありませんので、興味が無ければ読み飛ばして貰っても問題ありません。
DDR4は「DDR4 SDRAM」の略号で「DDR SDRAM」の規格の中の1つです。
もともとはSDRAM規格を改良したものが「DDR SDRAM」規格なのですが、前半の「DDR」は「Double-Data-Rate 」の略です。(データ転送レートが2倍のSDRAMという事)
通常は1Hzの場合は1秒に1回の動作なのですが、DDR規格についてはクロックの立ち上がりと立ち下がりに合わせて2回の動作を行う事で2倍の転送能力となります。
通常のSDRAMの2倍の転送速度を持つDDRですが、このDDRも進化を続けており「DDR」「DDR2」「DDR3」「DDR4」と数字が大きいほど高い能力を持っています。
全てクロックの立ち上がりと立下りに1回ずつのデータ転送を行う点では共通していますが、「DDR2」以降ではこれに加えてデータ転送時の前にあらかじめデータを取り出しておく「プリフェッチ」という技術が用いられるようになり、更に高速化しています。
「DDR」ではクロックの立ち上がりと立下りに1bit、合わせて2bitの通信でした。
1回「DDR2」では2bitの「プリフェッチ」、「DDR3」では4bit、「DDR4」では8bitをクロックの立ち上がりと立ち下がりにそれぞれ取り出します。
従って「SDRAM」に対して通信回数の増加により「DDR」は2倍、更に「プリフェッチ」により「DDR2」は4倍、「DDR3」は8倍、「DDR4」は16倍の転送力に相当するようになります。
ビデオカード(グラフィックボード)は一番こだわりたい部分
ゲーミングパソコンの3D処理に最も影響を及ぼすのがビデオカードです。
他のパーツに良い物を使っていても、ビデオカードがショボいと動きがカクカクになりますので、自分がどういう環境でどのようなゲームをやりたいのか良く考えて選びましょう。
因みにパソコンのゲームには必要動作環境や推奨環境と言うものがありますが、これはディスプレイの解像度にもよります。
FHD(1920×1080)の解像度であれば推奨環境を満たしておけば、人が極端に増えるような状況を除いてはサクサクにプレイできるでしょう。
ただし、4KのディスプレイになるとFHDの4倍の画素数になりまので負担がかなり大きくなり、FHDではサクサクだったものがカクカクになる事が多いです。
ディスプレイの解像度については22~3インチのものを使用している限り、FHDでも目の粗さは感じませんが、27インチ以上のものになるとFHDでは滲みや粗さを感じます。(一度4Kでプレイすると2度とFHDには戻れなくなるほど差があります)
実際に4Kの物を使用してみないと分からないと思いますが、FHDと比べると全く精細感や臨場感が異なりますので、将来的に4Kディスプレイの導入を少しでも考えているなら4K対応でなおかつハイスペックなビデオカードを選んだ方が良いと思います。
ただし、それが近い将来でなく2年後の話であるならば、FHD用のビデオカードにしておき、後でビデオカードを乗せ換えるのも手です。
ビデオカードのシェアはNVIDIAが8割程度を占める
CPUはインテルの1強でしたが、ビデオカードについてもAMDが不振でCPU以上にNVIDIAの1社の寡占状態となっています。
従ってCPU同様にゲーミングパソコンの自作初心者であれば、情報量が多いNVIDIAのGeForceシリーズを選んだ方が無難でしょう。
因みに「GeForce」はビデオカードの頭脳であるGPUチップ部分の事を指し、最終的にASUSなどメーカーがGPUチップとメモリー、冷却装置などと合わせてビデオカードとしてモジュール化して販売しています。
従ってGPUチップが同じでも、ビデオカードの段階になるとメーカーによって出力インターフェイスや冷却性能などが異なります。
2016~2017年現在のコンシューマーデスクトップ用GeFocreのラインナップは以下の6つのグレードとなります。
| GTX1050 | GTX1050Ti | GTX1060 | |
|---|---|---|---|
| 640コア | 768コア | 1152コア | 1280コア |
| ベースクロック 1290MHz | ベースクロック 1354MHz | ベースクロック 1506MHz |
|
| メモリ2GB | メモリ4GB | メモリ3GB | メモリ6GB |
| 転送能力112GB/秒 | 転送能力192GB/秒 | ||
| SLI不可 | |||
| 消費電力75W | 消費電力120W | ||
| 必要電源300W | 必要電源400W | ||
| GTX1070 | GTX1080 |
|---|---|
| 1920コア | 2560コア |
| ベースクロック 1506MHz | ベースクロック 1607MHz |
| メモリ8GB | メモリ8GB |
| 転送能力256GB/秒 | 転送能力320GB/秒 |
| SLI可 | |
| 消費電力150W | 消費電力180W |
| 必要電源500W | |
エントリークラスが「GTX1050」「GTX1050Ti」、ミドルクラスが「GTX1060 3GB」「GTX1060 6GB」、ハイエンドが「GTX1070」「GTX1080」の6モデルとなっていますが、3Dの処理能力はビデオカードで決まると言っても過言ではないので、ゲーミングパソコンを自作するならミドルクラス以上のビデオカードを選んだ方が後々後悔しないと思います。
現状の価格帯は「GTX1050」が1万円台前半、「GTX1050Ti」が1万円台後半、「GTX1060 3GB」が2万円台後半、「GTX1060 6GB」が3万円台前半、「GTX1070」が4万円台後半、「GTX1080」が7万円台後半となっています。
予算があればなるべく良い物を選びたいところですが、コストパフォーマンスを考えると「GTX1060 6GB」、「GTX1070」辺りが最もおすすめなところではないかと思います。
特に4Kのディスプレイを使用する場合には「GTX1070」以上を入れていきたいところです。
では、ここからは「GTX1060~1080」を搭載したビデオカードのメーカー別のスペックを比較していきます。
かなりメーカー数が多く全ては紹介しきれないので、シェアの高い「GIGABYTE」「MSI」「ASUS」「ZOTAC」の4ブランドに絞って比較を行います。
各メーカーの中でも同じGPUを使用して動作クロックを上げたものやGPUクーラーの数が違う物、空冷ではなく水冷クーラーを搭載した物があり、かなり種類が多く分かりにくいのですがそれぞれメーカー別に比較を行います。
「GTX1060 3GB」を搭載したビデオカード
「GIGABYTE」の「GTX1060 3GB」は次の3モデルがリリースされています。
| GIGABYTE「GTX1060 3GB」 | ||
|---|---|---|
GV-N1060IXOC-3GD | GV-N1060WF2OC-3GD | GV-N1060G1 Gaming-3GD |
| 25,855円 | 24,107円 | 28,041円 |
| Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ |
| 1556MHz | 1582MHz | 1620MHz |
| 空冷ファン×1 | 空冷ファン×2 | 空冷ファン×2 |
| 補助電源6ピン×1 | 補助電源6ピン×1 | 補助電源8ピン×1 |
| DVI-D×2 | DVI-D×2 | DVI-D×1 |
| HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 |
| DisplayPort×1 | DisplayPort×1 | DisplayPort×3 |
こちらの3モデルの主な違いは動作クロック・サイズ・ファンの数・出力インターフェイスの数です。
1ファンの物は省スペースパソコン用で価格が高い割に性能は低いのでこの3モデルであれば真ん中の「GV-N1060WF2OC-3GD」、ゲームで3画面使用したいなら「GV-N1060G1 Gaming-3GD」という選択になるでしょう。
「MSI」の「GTX1060 3GB」も同様に3モデルの展開になっています。
| MSI「GTX1060 3GB」 | ||
|---|---|---|
MSI GTX1060 3G OC | MSI GTX1060 ARMOR 3G OCV1 | MSI GTX1060 GAMING X 3G |
| 23,130円 | 25,949円 | 27,949円 |
| Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ |
| 1544MHz | 1544MHz | 1594MHz |
| 空冷ファン×1 | 空冷ファン×2 | 空冷ファン×2 |
| 補助電源6ピン×1 | 補助電源8ピン×1 | 補助電源8ピン×1 |
| DVI-D×1 | DVI-D×1 | DVI-D×1 |
| HDMI×1 | HDMI×2 | HDMI×1 |
| DisplayPort×3 | DisplayPort×2 | DisplayPort×3 |
こちらも同様に省スペースモデルとクロック数の違いになりますが、「GIGABYTE」のモデルに比べると動作クロックを若干低めに抑えてあります。
価格帯もそれぞれ「GIGABYTE」と変わりませんので「MSI」を選ぶよりは「GIGABYTE」のビデオカードを選んだ方が良いと思います。
「ASUS」と「ZOTAC」からは合わせて3モデルのラインナップとなります。(国内流通はそのうち2モデル)
| ASUS「GTX1060 3GB」 | ZOTAC「GTX1060 3GB」 |
|---|---|
ASUS DUAL-GTX1060-O3G  | ZOTAC ZT-P10610A-10L  |
| 27,950円 | 24,204円 |
| Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ |
| 1594MHz | 1506MHz |
| 空冷ファン×2 | 空冷ファン×1 |
| 補助電源6ピン×1 | 補助電源6ピン×1 |
| DVI-D×1 | DVI-D×1 |
| HDMI×2 | HDMI×1 |
| DisplayPort×2 | DisplayPort×3 |
こちらはAUSUの「DUAL-GTX1060-O3G 」が動作クロックがかなり高めに設定されていますが、さほどクロックが変わらない「GIGABYTE」の「GV-N1060WF2OC-3GD」の方が実勢価格が数千円安く推移しています。
従って「GTX1060 3GB」であれば「GIGABYTE」の「GV-N1060WF2OC-3GD」が最もコストパフォーマンスが高いと言えます。
GIGABYTE GTX 1060 GV-N1060WF2OC-3GD
「GTX1060 6GB」を搭載したビデオカード
「GIGABYTE」の「GTX1060 6GB」は次の4モデルがリリースされています。
| GIGABYTE「GTX1060 6GB」 | |||
|---|---|---|---|
GV-N1060IXOC-6GD | GV-N1060WF2OC-6GD | GV-N1060G1 GAMING-6GD | GV-N1060XTREME-6GD |
| 32,310円 | 32,742円 | 33,980円 | 40,200円 |
| Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ |
| 1556MHz | 1582MHz | 1620MHz | 1645MHz |
| 空冷ファン×1 | 空冷ファン×2 | 空冷ファン×2 | 空冷ファン×2 |
| 補助電源6ピン×1 | 補助電源6ピン×1 | 補助電源8ピン×1 | 補助電源8ピン×1 |
| DVI-D×2 | DVI-D×2 | DVI-D×1 | DVI-D×1 |
| HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 |
| DisplayPort×1 | DisplayPort×1 | DisplayPort×3 | DisplayPort×3 |
基本的な構成は3GBモデルと変わりませんが、最上位に1645MHzのOC7モデルが追加されています。
MSIは完全に3GBモデルと同様の構成で3モデルの展開となっています。
| MSI「GTX1060 6GB」 | ||
|---|---|---|
MSI GTX1060 6G OC | MSI GTX1060 ARMOR 6G OCV1 | MSI GTX 1060 GAMING X 6G |
| 29,760円 | 31,760円 | 33,782円 |
| Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ |
| 1544MHz | 1544MHz | 1594MHz |
| 空冷ファン×1 | 空冷ファン×2 | 空冷ファン×2 |
| 補助電源6ピン×1 | 補助電源8ピン×1 | 補助電源8ピン×1 |
| DVI-D×1 | DVI-D×1 | DVI-D×1 |
| HDMI×1 | HDMI×2 | HDMI×1 |
| DisplayPort×3 | DisplayPort×2 | DisplayPort×3 |
価格と動作クロックのバランスを考えるとコストパフォーマンスは「GIGABYTE」に劣る印象です。
このグレードになるとASUSはしっかりと品揃えをしており、4モデルのラインナップになっています。
| ASUS「GTX1060 3GB」 | |||
|---|---|---|---|
ASUS TURBO-GTX1060-6G | ASUS STRIX-GTX1060-DC2O6G | ASUS DUAL-GTX1060-O6G | ASUS STRIX-GTX1060-O6G-GAMING |
| 30,270円 | 32,647円 | 33,480円 | 34,360円 |
| Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ |
| 1506MHz | 1595MHz | 1594MHz | 1645MHz |
| 空冷ファン×1 | 空冷ファン×2 | 空冷ファン×2 | 空冷ファン×3 |
| 補助電源6ピン×1 | 補助電源6ピン×1 | 補助電源6ピン×1 | 補助電源8ピン×1 |
| DVI-D×1 | DVI-D×1 | DVI-D×1 | DVI-D×1 |
| HDMI×2 | HDMI×2 | HDMI×2 | HDMI×2 |
| DisplayPort×2 | DisplayPort×2 | DisplayPort×2 | DisplayPort×2 |
この中で注目したいのが最上位の3FANモデルで、やや電力的には大き目になりますがクロックは「GIGABYTE」の最上位モデルと同等で冷却性能も充分な印象です。
価格も「GIGABYTE」の物よりも安いので「GTX1060 6GB」中では最も狙い目なモデルではないかと思います。
ZOTACについては2モデルのラインナップになっていますが、最低クロックの物であれば全メーカーの中で価格が最も安くなっています。
| ZOTAC「GTX1060 6GB」 | |
|---|---|
ZOTAC ZT-P10600A-10L | ZOTAC ZT-P10600B-10M |
| 26,761円 | 30,700円 |
| Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ |
| 1506MHz | 1556MHz |
| 空冷ファン×1 | 空冷ファン×2 |
| 補助電源6ピン×1 | 補助電源6ピン×1 |
| DVI-D×1 | DVI-D×1 |
| HDMI×1 | HDMI×1 |
| DisplayPort×3 | DisplayPort×3 |
従って「GTX1060 6GB」を価格で選ぶならZOTACの1FANモデル、性能で選ぶならASUSの3FANモデルがおすすめとなります。
ASUST NVIDIA STRIX-GTX1060-O6G-GAMING
「GTX1070」を搭載したビデオカード
「GIGABYTE」の「GTX1070」は次の4モデルがリリースされています。
| GIGABYTE「GTX1070」 | |||
|---|---|---|---|
GV-N1070IXOC-8GD | GV-N1070WF2OC-8GD | GV-N1070G1 Gaming-8GD | GV-N1070XTREME-8GD |
| 49,477円 | 49,339円 | 48,212円 | 59,918円 |
| Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ |
| 1556MHz | 1582MHz | 1620MHz | 1695MHz |
| 空冷ファン×1 | 空冷ファン×2 | 空冷ファン×3 | 空冷ファン×3 |
| 補助電源8ピン×1 | 補助電源8ピン×1 | 補助電源8ピン×1 | 補助電源8ピン×1 |
| DVI-D×2 | DVI-D×1 | DVI-D×1 | DVI-D×1 |
| HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 |
| DisplayPort×1 | DisplayPort×3 | DisplayPort×3 | DisplayPort×3 |
価格帯的には4~5万円程度になっていますが、この中では上から2番目のモデル、1620MHzの「GV-N1070G1 Gaming-8GD」がコストパフォーマンスが高いと感じます。
その上のモデルになると6万円に近くなり、「GTX1080」の下位モデルとの価格差が1万円台となってしまいます。
「MSI」の「GTX1070」は同様に4モデルがリリースされています。
| MSI「GTX1070」 | |||
|---|---|---|---|
MSI GTX 1070 ARMOR 8G OC | MSI GTX 1070 GAMING X 8G | MSI GTX 1070 GAMING Z 8G | MSI GTX1070 SEA HAWK X |
| 45,580円 | 52,429円 | 60,280円 | 69,800円 |
| Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ |
| 1556MHz | 1607MHz | 1657MHz | 1607MHz |
| 空冷ファン2 | 空冷ファン×2 | 空冷ファン×2 | 水冷ファン×1 |
| 補助電源8ピン×1 | 補助電源6ピン×1 補助電源8ピン×1 | 補助電源6ピン×1 補助電源8ピン×1 | 補助電源8ピン×1 |
| DVI-D×1 | DVI-D×1 | DVI-D×1 | DVI-D×1 |
| HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 |
| DisplayPort×3 | DisplayPort×3 | DisplayPort×3 | DisplayPort×3 |
同スペックの物であれば「GIGABYTE」の方が安く、水冷モデルに関してはほぼ「GTX1080」と変わらない価格帯となります。
「ASUS」の「GTX1070」は同様に4モデルがリリースされています。
| ASUS「GTX1070」 | |||
|---|---|---|---|
ASUS TURBO-GTX1070-8G | ASUS DUAL-GTX1070-O8G | ASUS STRIX-GTX1070-8G-GAMING | ASUS STRIX-GTX1070-O8G-GAMING |
| 48,745円 | 50,436円 | 53,676円 | 53,676円 |
| Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ |
| 1506MHz | 1607MHz | 1531MHz | 1657MHz |
| 空冷ファン×1 | 空冷ファン×2 | 空冷ファン×3 | 空冷ファン×3 |
| 補助電源8ピン×1 | 補助電源8ピン×1 | 補助電源8ピン×1 | 補助電源8ピン×1 |
| DVI-D×1 | DVI-D×1 | DVI-D×1 | DVI-D×1 |
| HDMI×2 | HDMI×2 | HDMI×1 | HDMI×2 |
| DisplayPort×2 | DisplayPort×2 | DisplayPort×3 | DisplayPort×2 |
最上位の1657MHzモデルについては、他社よりも1割程度価格が安くなっていますのでハイエンドについてはASUSのモデルがおすすめです。
「ZOTAC」の「GTX1070」は同様に3モデルがリリースされています。
| ZOTAC「GTX1070」 | ||
|---|---|---|
ZOTAC ZT-P10700K-10M | ZOTAC ZT-P10700C-10P | ZOTAC ZT-P10700B-10P |
| 47,200円 | 46,781円 | 59,000円 |
| Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ |
| 1518MHz | 1607MHz | 1632MHz |
| 空冷ファン×2 | 空冷ファン×2 | 空冷ファン×2 |
| 補助電源8ピン×1 | 補助電源8ピン×2 | 補助電源8ピン×2 |
| DVI-D×1 | DVI-D×1 | DVI-D×1 |
| HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 |
| DisplayPort×3 | DisplayPort×3 | DisplayPort×3 |
「GTX1070」についてはハイエンドクラスになると価格が6万円近くなり、「GTX1080」との価格差が1万円台になってしまいますので、おすすめはASUSの1657MHz、「STRIX-GTX1070-O8G-GAMING」辺りになります。
「GTX1080」を搭載したビデオカード
「GIGABYTE」の「GTX1080」は次の3モデルがリリースされています。
| GIGABYTE「GTX1080」 | ||
|---|---|---|
GV-N1080G1 Gaming-8GD | GV-N1080XTREME GAMING-8GD-PP | GV-N1080XTREME W-8GD |
| 76,980円 | 98,954円 | 97,363円 |
| Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ |
| 1721MHz | 1784MHz | 1784MHz |
| 空冷ファン×3 | 空冷ファン×3 | 水冷ファン×1 |
| 補助電源8ピン×1 | 補助電源8ピン×2 | 補助電源8ピン×2 |
| DVI-D×1 | DVI-D×1 | DVI-D×1 |
| HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 |
| DisplayPort×3 | DisplayPort×3 | DisplayPort×3 |
1721MHzが空冷、1784MHz は空冷と水冷となっていますが性能差の割に価格差が大きい為、 1721MHzのモデルが最もコストパフォーマンスが高そうです。
「MSI」の「GTX1080」は次の4モデルがリリースされています。
| MSI「GTX1080」 | |||
|---|---|---|---|
MSI GTX1080 ARMOR 8G OC | MSI GeForce GTX 1080 GAMING X 8G | MSI GeForce GTX 1080 SEA HAWK X | MSI GeForce GTX 1080 GAMING Z 8G |
| 80,784円 | 84,556円 | 97,178円 | 112,000円 |
| Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ |
| 1657MHz | 1708MHz | 1708MHz | 1771MHz |
| 空冷ファン2 | 空冷ファン×2 | 水冷ファン×1 | 空冷ファン×2 |
| 補助電源6ピン×1 補助電源8ピン×1 | 補助電源6ピン×1 補助電源8ピン×1 | 補助電源8ピン×1 | 補助電源6ピン×1 補助電源8ピン×1 |
| DVI-D×1 | DVI-D×1 | DVI-D×1 | DVI-D×1 |
| HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 |
| DisplayPort×3 | DisplayPort×3 | DisplayPort×3 | DisplayPort×3 |
いずれのモデルも「GIGABYTE」に比べるとクロック数と価格のバランスが悪く、なかなかおすすめしにくい価格帯となっています。
「ASUS」の「GTX1080」は次の4モデルがリリースされています。
| ASUS「GTX1080」 | |||
|---|---|---|---|
ASUS TURBO-GTX1080-8G | ASUS STRIX-GTX1080-8G-GAMING | ASUS STRIX-GTX1080-A8G-GAMING | ASUS STRIX-GTX1080-O8G-GAMING |
| 80,930円 | 79,947円 | 78,246円 | 96,870円 |
| Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ |
| 1607MHz | 1632MHz | 1695MHz | 1784MHz |
| 空冷ファン×1 | 空冷ファン×3 | 空冷ファン×3 | 空冷ファン×3 |
| 補助電源8ピン×1 | 補助電源6ピン×1 補助電源8ピン×1 | 補助電源6ピン×1 補助電源8ピン×1 | 補助電源6ピン×1 補助電源8ピン×1 |
| DisplayPort×2 | DisplayPort×3 | DisplayPort×2 | DisplayPort×2 |
| DVI-D×1 | DVI-D×1 | DVI-D×1 | DVI-D×1 |
| HDMI×2 | HDMI×1 | HDMI×2 | HDMI×2 |
こちらも同様にクロック周波数と価格のバランスを考えると「GIGABYTE」に劣っている印象です。
「ZOTAC」の「GTX1080」は次の4モデルがリリースされています。
| ZOTAC「GTX1080」 | |||
|---|---|---|---|
ZOTAC ZT-P10800C-10P | ZOTAC ZT-P10800B-10P | ZOTAC ZT-P10800F-30P | ZOTAC ZT-P10800G-30P |
| 75,384円 | 91,000円 | 121,542円 | 140,000円 |
| Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ |
| 1683MHz | 1771MHz | 1632MHz | 1657MHz |
| 空冷ファン×2 | 空冷ファン×2 | 水冷ファン×1 | 水冷ファン×1 |
| 補助電源8ピン×2 | 補助電源8ピン×2 | 補助電源8ピン×2 | 補助電源8ピン×2 |
| DVI-D×1 | DVI-D×1 | DVI-D×1 | DVI-D×1 |
| HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 |
| DisplayPort×3 | DisplayPort×3 | DisplayPort×3 | DisplayPort×3 |
このうち水冷の2モデルはかなり価格が高いですが、1683MHzのモデルに関してはかなり価格が安いのですが、「GIGABYTE」の1721MHzのモデルの価格が安すぎる為、「GTX1080」搭載のビデオカードのおすすめは「GIGABYTE」の「GV-N1080G1 Gaming-8GD」になります。
GIGABYTE GV-N1080G1 GAMING-8GD
記憶装置はSSDを選ぶべき
ゲーミングパソコンを自作する上でこれからわざわざHDDを選択する人は少ないと思いますが、SSDのメリットを再確認しておきましょう。
SSDはHDDと比べるとOSやゲームの起動がかなり早くなるばかりではなく、ゲーム中でもクライアントソフトからの他のキャラクターなどの読み込みがとてつもなく早くなります。
従ってゲーミングパソコンを自作するのであればSSDの一択になります。
ただ、このSSDには現状選択し得る規格が2種類あります。
1つ目は従来のSATA3.0のコネクタで接続するタイプのSSDで、もう一つは2年位前から市場に出回り始めたPCI-e3.0スロットに挿すタイプのM.2規格のSSDです。
両者の理論上の転送速度は4~5倍もの差がありますので、出来れば容量を抑えてでもM.2タイプのSSDを選びたいところです。
因みにこのM.2タイプのSSDの中にもいくつも種類があり、内部インターフェースがSATA3の為に転送速度が従来のSATA3に準拠するものもあります。
速度を求めるのであれば、内部インターフェイスが最新のM.2 NVMe (Gen 3×4)の物を選ぶ必要があります。
Gen3(第三世代)の場合には1レーン当たりの転送速度が985MB/Sとなりますので、4レーンの×4の物であれば理論上は4GB/Sの転送速度となり、SATA3のSSDと比べると理論上では8倍の転送能力となります。
256GB M.2 NVMe (Gen 3×4) SSDの比較
ゲーミングパソコンで重要なのは読み込みの速さなので読み込み速度が速い順に並べています。
| Samsung | Phison | PLEXTOR | PLEXTOR | Intel |
|---|---|---|---|---|
| MZVPW256HEGL-00000 | PHM2-256GB | PX-256M8PeGN-06 | PX-256M8PeG-08 | SSDPEKKW256G7X1 |
| 27,000円 | 13,000円 | 14,666円 | 16,980円 | 12,600円 |
| Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ |
| 読み3100MB/s | 読み2750MB/s | 読み2000MB/s | 読み2000MB/s | 読み1570MB/s |
| 書き1400MB/s | 書き1550MB/s | 書き900MB/s | 書き900MB/s | 書き540MB/s |
| 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB |
価格と速度のバランスを考えるとPhisonのSSDが良いバランスですが、動作の安定性や情報量を考えると多少速度を犠牲にしてもインテルのSSDを選んだ方が良いような気がします。
M.2 NVMeの規格自体が新しいものなので、なるべく信頼度の高いメーカーが無難な選択だと思います。
もう少し容量が欲しい場合や従来方のSATA3のSSDの方が安心だという場合には次の項目を参照して下さい。
500GB SATA3 SSDの比較
500GB前後のSATA 6GB対応のSSDを読み込み速度の速い順に並べると以下の表の通りとなります。
| Transcend | CFD | Crucial | Transcend | Samsung | Crucial |
|---|---|---|---|---|---|
TS512GSSD370S | CSSD-S6O480NCG1Q | CT500MX200SSD1 | TS480GSSD220S | MZ-750500B/IT  | CT525MX300SSD1 |
| 20,200円 | 13,400円 | 16,800円 | 14,420円 | 12,980円 | 13,971円 |
| Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 | Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ |
| 読み570MB/s | 読み560MB/s | 読み555MB/s | 読み550MB/s | 読み540MB/s | 読み530MB/s |
| 書き470MB/s | 書き510MB/s | 書き500MB/s | 書き450MB/s | 書き520MB/s | 書き510MB/s |
| 512GB | 480GB | 500GB | 480GB | 500GB | 525GB |
トランセンドの512GBモデルが570MB/sと最速ですが、価格がかなり高く、コストパフォーマンスを考えるとCFD の480GBモデル、「CSSD-S6O480NCG1Q」が560MB/sとトランセンドに次ぐ高速読み込みが可能でおすすめです。
「LGA1150」ソケット対応のマザーボード
1995年以降のマザーボードの規格は「ATX」が主流になっていますが、この規格で表現されるのはマザーボードの大きさや電源ユニット、ドライブベイの配置などで、他にも「micro-ATX」などの小型のPC向けの規格もありますが、ゲーミングPCであれば、やや大型のケースに対応する「ATX」規格一択と考えて差し支えないでしょう。
この「ATX」という物理的な各種パーツの配置に加えて、その中でもCPUのソケット形状を含む搭載チップセットの違いがあります。
intel第6世代以降のCPUに対応する「LGA1150」ソケットを搭載しているコンシューマー向けの「ATX」マザーボードのチップセットは「Z170」「H170」「H110」の3種類です。
※第7世代のCPUである7700系にもBIOSアップデートで対応
第6世代の6700系のCPUと組み合わせるならこれらのマザーボードがおすすめです。
このうち「H110」は安価ですがメモリスロットがチャンネル当たり1枚分しかなく、USBポートも少ないなど廉価PC向けの構成となっていますので、ゲーミングPC向けのマザーボードは最上位の「Z170」、ミドルクラスの「H170」搭載のモデルになります。
「Z170」と「H170」の大きな違いは、PCI-E3.0のレーン数(実際にデータの転送に使用できる帯域)が20レーン/16レーンの差と、オーバークロックの可否などが挙げられます。
「H170」でも最大の性能を引き出すにはかなり拡張機能を使いこなす事になりますが、将来的にグラボ2枚挿しなどを試す可能性があるのならば「Z170」がおすすめです。
最上位の「Z170」の中にも1万円台のモデルはありますので、ゲーミングPCであれば「Z170」を基準に考えた方が後々後悔しないでしょう。
また、1月に発売された第7世代向けに開発されたマザーボードには「Z270」「H270」の2種類があります。
これらの違いも同様にPCI-E3.0のレーン数(実際にデータの転送に使用できる帯域)が24レーン/20レーンの差と、オーバークロックの可否などが挙げられます。
1世代前の「Z170」「H170」よりも最大レーン数が4ずつ増えていますが、この差を体感出来るような環境はおいそれとは作れないと思いますので、「Z270」「H270」を選ぶメリットはあまりないのですがBIOSアップデートなしで7700系を使いたいのであればこちらを選ぶ必要があります。
※6600系から7700系への換装なら「Z170」「H170」でも良いですが、ゼロから組み上げる場合、7700系に対応させる為にアップデートしようにも7700系のCPUではBIOSが起動しない可能性大
ここからは6600系と7700系を前提に「Z170」「Z270」のマザーボードを比較して行きます。
「Z170」を搭載したマザーボードの比較
マザーボードについては「ASUS」「ASRock」「GIGABYTE」の3社で市場の9割程度のシェアを占めており、1位の「ASUS」が約50%、2位の「ASRock」が25%、3位の「GIGABYTE」が20%弱となっていますが、「ASRock」は「ASUS」の子会社となっていますので、実質的には「ASUS」が75程度のシェアを占めていると言えます。
ざっくりとした特徴は「ASUS」は高品質な上にBIOSやマニュアルが日本語化されていたりとソフトウェア部分のユーザビリティが高く、「ASRock」は高品質で価格が安く、「GIGABYTE」は高品質ではあるものの、ソフトウェアがやや使いにくいと言った形です。
PC自作初心者であれば「ASUS」のマザーボードがおすすめですが、他のメーカーに比べて価格が高いのが難点です。
その中でも比較的リーズナブルな価格の物が次の3モデルになります。
※全てのマザーボードのPCI-E3.0×16については()内に使用レーン数を記載していますが、2スロット(16レーン使用)である場合、グラボを2枚挿しにした場合(8+8)で動作する事を意味します。3枚挿しの場合には8+8+4=20レーンになります。
| ASUS | |||
|---|---|---|---|
| 型番 | Z170-K | Z170 PRO GAMING | Z170-A |
| 参考価格 | 15,959円 | 18,200円 | 22,236円 |
| 最新価格 | Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ |
| NVIDIA SLI | × | ○ | ○ |
| PCI-E3.0×16 | 1スロット(16レーン使用) | 2スロット(16レーン使用) | |
| PCI-E3.0×16 | 1スロット (4レーン使用) | 1スロット (4レーン使用) | |
| PCI-E3.0×1 | 2スロット | 3スロット | |
| PCI | 2スロット | - | 1スロット |
| M.2×4 | 1 | 1 | 1 |
| SATA 6GB | 6 | 4 | 6 |
| SATA Express | 1 | 1 | 1 |
| USB 3.1 | 2 | 2 | 2 |
| USB 3.0 | - | 4 | 2 |
| USB 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| メモリ | 2CH~ | ||
| 4スロット | |||
| 最大64GB | |||
| 2133~3466MHz | 2133~3400MHz | 2133~3466MHz | |
このうち真ん中の「Z170 PRO GAMING」は内蔵のサウンドボードの音質が良く、ゲームに特化した構成となっています。
SATA6.0ポートはやや少ないですが、SSDをM.2×4に接続する前提なら必要充分だと思います。
ASUSTeK Intel Z170搭載 ゲーミングマザーボード LGA1151対応 Z170-PRO GAMING 【ATX】
「ASRock」の「Z170」搭載のエントリークラスは以下の3モデルになります。
| ASRock | |||
|---|---|---|---|
| 型番 | Z170 Pro4  | Z170 Gaming K4 | Z170 Extreme4 |
| 参考価格 | 13,480円 | 15,820円 | 15,560円 |
| 最新価格 | Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ |
| NVIDIA SLI | × | × | ○ |
| PCI-E3.0×16 | 2スロット(16レーン使用) | ||
| PCI-E3.0×16 | - | 1スロット (4レーン使用) | |
| PCI-E3.0×1 | 3スロット | 1スロット | |
| M.2×4 | 1 | 1 | 1 |
| SATA 6GB | 6 | 6 | 6 |
| SATA Express | 2 | 2 | 1 |
| USB 3.1 | - | - | 2 |
| USB 3.0 | 8 | 8 | 6 |
| USB 2.0 | - | - | - |
| メモリ | 2CH~ | ||
| 4スロット | |||
| 最大64GB | |||
| 2133~3866MHz | 2133~3866MHz | 2133~3466MHz | |
このうちNVIDIAのSLIに対応しているのは「Z170 Extreme4」のみとなりますが、ASUSの「Z170 PRO GAMING」とほぼ同等のスペックとなっています。
価格で選ぶなら、ドスパラでは「Z170 Extreme4」+「Core i7 6700K」+メモリのセット割引を行っていますのでこのモデルを選んでも良いかと思います。
「GIGABYTEの「Z170」搭載のエントリークラスは以下の3モデルになります。
| GIGABYTE | |||
|---|---|---|---|
| 型番 | GA-Z170-HD3P | GA-Z170X-UD3 | GA-Z170X-Gaming 3 |
| 参考価格 | 10,800円 | 12,900円 | 15,900円 |
| 最新価格 | Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ |
| NVIDIA SLI | × | ○ | ○ |
| PCI-E3.0×16 | 1スロット(16レーン使用) | 2スロット(16レーン使用) | |
| PCI-E3.0×16 | 1スロット (4レーン使用) | ||
| PCI-E3.0×1 | 2スロット | 3スロット | |
| PCI | 2スロット | - | |
| M.2×4 | 1 | 2 | 2 |
| SATA 6GB | 6 | 6 | 6 |
| SATA Express | 3 | 3 | 3 |
| USB 3.1 | 2 | 2 | 2 |
| USB 3.0 | 3 | 3 | 3 |
| USB 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| メモリ | 2CH~ | ||
| 4スロット | |||
| 最大64GB | |||
| 2133~3466MHz | |||
基本スペック的な部分では「GA-Z170X-UD3」でも充分ですので、コストパフォーマンスだけで考えれば3社の中でも「GA-Z170X-UD3」が最もおすすめですが、あとは情報量の多さや扱い易さの部分で5000円程高くなる「ASUS」のモデルとどちらが良いか考える必要があるでしょう。
GIGABYTE Intel Z170チップセット搭載 GA-Z170X-UD3
「Z270」を搭載したマザーボードの比較
ASUSの「Z270」を搭載したマザーボードのおすすめモデルは以下の3つになります。
| ASUS | |||
|---|---|---|---|
| 型番 | PRIME Z270-K | PRIME Z270-A | STRIX Z270F GAMING |
| 参考価格 | 21,384円 | 23,799円 | 24,800円 |
| 最新価格 | Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ |
| NVIDIA SLI | × | ○ | ○ |
| PCI-E3.0×16 | 1スロット(16レーン使用) | 2スロット(16レーン使用) | |
| PCI-E3.0×16 | 1スロット (4レーン使用) | ||
| PCI-E3.0×1 | 2スロット | 4スロット | |
| PCI | - | ||
| M.2×4 | 2 | 2 | 2 |
| SATA 6GB | 6 | 6 | 6 |
| USB 3.1 | 2 | 2 | - |
| USB 3.0 | - | 4 | 4 |
| USB 2.0 | 2 | - | - |
| メモリ | 2CH~ | ||
| 4スロット | |||
| 最大64GB | |||
| 2133~3866MHz | |||
基本的には「Z170」と変わらず、ゲーミングモデルの「STRIX Z270F GAMING」が高音質のサウンドチップを搭載しています。
将来的にSLIも考慮しているなら「PRIME Z270-A」「STRIX Z270F GAMING」、サウンドカードを追加するかしないかで選ぶモデルは変わりますが、「STRIX Z270F GAMING」はオンボードでもかなり音質は良いようです。
この辺りは感覚の問題なのでとりあえずちょっと良い音でというのであれば「STRIX Z270F GAMING」がおすすめです。
後でサウンドカードを追加する予定なら「PRIME Z270-A」の方が良いでしょう。
「ASRock」の「Z270」搭載のエントリークラスは以下の3モデルになります。
| ASRock | |||
|---|---|---|---|
| 型番 | Z270 Pro4  | Z270 Extreme4 | Fatal1ty Z270 Gaming K6 |
| 参考価格 | 17,980円 | 22,480円 | 27,300円 |
| 最新価格 | Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ |
| NVIDIA SLI | × | ○ | ○ |
| PCI-E3.0×16 | 2スロット(16レーン使用) | 2スロット(16レーン使用) | |
| PCI-E3.0×16 | - | 1スロット (4レーン使用) | |
| PCI-E3.0×1 | 3スロット | ||
| PCI-E2.0 | - | - | - |
| PCI | 1 | - | - |
| M.2×4 | 2 | 2 | 2 |
| SATA 6GB | 6 | 8 | 8 |
| USB 3.1 | - | 2 | 2 |
| USB 3.0 | 7 | 8 | 8 |
| USB 2.0 | - | - | - |
| メモリ | 2CH~ | ||
| 4スロット | |||
| 最大64GB | |||
| 2133~3733MHz | 2133~3866MHz | ||
USBの拡張性は高いですが、ASUSのマザーボードと比べて価格的なメリットはない感じですね。
「GIGABYTE」の「Z270」搭載のエントリークラスはまだ発売されておらず、ハイエンドクラスのみのラインナップになっています。
| GIGABYTE | |||
|---|---|---|---|
| 型番 | GA-Z270X-Ultra Gaming  | GA-Z270X-Gaming 5 | GIGABYTE Gaming 7 |
| 参考価格 | 23,544円 | 27,497円 | 36,094円 |
| 最新価格 | Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ |
| NVIDIA SLI | ○ | ○ | ○ |
| PCI-E3.0×16 | 1スロット(16レーン使用) | ||
| PCI-E3.0×16 | 1スロット (8レーン使用) | ||
| PCI-E3.0×16 | 1スロット (4レーン使用) | ||
| PCI-E3.0×1 | 3スロット | ||
| M.2×4 | 1 | 2 | 2 |
| SATA 6GB | 6 | 6 | 6 |
| SATA Express | 3 | 3 | 3 |
| USB 3.1 | 6 | 2 | 2 |
| USB 3.0 | - | 3 | 4 |
| USB 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| メモリ | 2CH~ | ||
| 4スロット | |||
| 最大64GB | |||
| 2133~3866MHz | 2133~4000MHz | ||
こちらもASUSのマザーボードとあまり価格差がないので、現状では「GIGABYTE」のマザーボードを選ぶメリットは少ないと思います。
光学ドライブは有ってもなくても良いが?
一昔前まではOSのインストールは光学ドライブからディスクを使用して行うのが一般的でしたので光学ドライブは必須でしたが、現状ではOSをネットでダウンロードしてUSBストレージからインストールする事が可能になっています。
また、各種ソフトウェアもダウンロード形式が主流になって来ていますので光学ドライブはなくても構わないのですが、CDやDVDなどをPCに落とす場合を想定するなら光学ドライブが必要になります。
ブルーレイのHD解像度の物であればブルーレイ対応、そうでなければDVD対応の物を選べば良いでしょう。
DVDなら2000円程度~、ブルーレイなら8000円程度~となってます。
電源ユニットは500W以上のものを選ぶ
電源ユニットは選択するCPUやビデオカードにもよりますが、Core i7 6700K+GTX1070~1080という組み合わせであれば最低でも500W、将来的にSLIなどでビデオカードを2枚挿しする可能性があるのならば700W程度は欲しいところです。
価格によっては静穏性にかなり差が出ますが、今回は静穏性は考慮せず、なるべく安いモデルをチョイスします。
| 玄人志向 | AeroCool | 玄人志向 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 500W | 600W | 650W | 750W | 750W | 800W |
KRPW-L5-500W/80+ | KRPW-L5-600W/80+ | KRPW-AK650W/88+ | KRPW-AK750W/88+ | VP-750 | KRPW-PT800W/92+ REV2.0  |
| 3,920円 | 4,610円 | 7,234円 | 7,780円 | 7,780円 | 11,772円 |
| Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ | Amazon 楽天市場 ドスパラ |
| PCI-E補助電源 | |||||
| 6+2ピン×1 6ピン×1 | 6+2ピン×1 6ピン×1 | 6+2ピン×2 | 6+2ピン×4 | 6+2ピン×4 | 6+2ピン×4 |
ビデオカード枚固定であれば玄人志向の「KRPW-L5-600W/80+」、ビデオカード2枚挿しでも700Wもあれば充分かと思いますので、おすすめは玄人志向の「KRPW-AK750W/88+」となります。
PCケースは冷却面で有利なミドルタワーがおすすめ
PCケースを選ぶ上で注意したいのが大きさですが、ゲーミングであれば冷却性能を優先してなるべく大型のものを選びたいところです。
PCケースの大きさの規格は、高さが40cm程度までがミニタワー、45cm以上がミドルタワー、55cm以上がフルタワーと呼ばれています。
フルタワーは価格が高くなりがちですので、おすすめはミドルタワーです。
因みにPCI-E3.0のビデオカードの大きさは、標準的なもので41×280×114 mm程度になりますので、ミドルタワーのケースであれば干渉する事はありません。
また、よほど特殊なCPUファンを取り付けるようでなければ、ケースには干渉しませんのでミドルタワーのケースで問題はありません。
ミドルタワーのケースを選ぶポイントは、フロントのUSB3.0/2.0端子の数、ケースファンの数、追加で設置可能なケースファンの数、デザインなどです。
ケースファンは通常のグラボ1枚挿しの環境であれば、吸気×1・排気×1で問題ないと思いますが、発熱量の多いグラボなどを使用したり、SLIで2枚挿しにする場合には追加で吸排気のケースファンを設置したいところです。
従って以後の拡張を意識するなら、天板や底版、サイドパネルにファンが設置出来るデザインのものが好ましく、そうでないならデザインが好みのものを選べば良いと思います。
個人的に良さそうだなと感じるのはこちらのPCケースです。
ENERMAX ECA3290B (COENUS) ブラック

こちらのPCケースは価格が6千円台ながら、フロントに1ファン付属で上下とサイドにもファンを追加する事が出来る、排熱性に優れたケースです。
ただし、排熱性が優れたケースはそれだけ吸い込むホコリの量も増えますので、吸気側フィルターなどを自作で取り付けるかこまめにエアスプレーなどでホコリを吹き飛ばすなどのメンテナンスが必要です。
ELECOM エアダスター ECO 逆さ使用OK ノンフロンタイプ 3本セット AD-ECOMT
KのつくCPUはクーラーが付属しない
繰り返しになりますが、7700K・6700Kの場合にはCPUクーラーが付属しませんので別途手配する必要があります。
オーバークロックが前提でなければ空冷で問題ありませんが、空冷であれば比較的大きなものになりますので水冷を選ぶ手もあります。
サイズ 【HASWELL対応】 虎徹 12cmサイドフロー SCKTT-1000
ただし、水冷のクーラーでもあまり冷えないものもありますし、CPUだけでなくグラボの熱が問題になる事も多いので、それならケースファンを増設してケース内の空気の流れを良くする方法を考えた方が良いのではないかと思います。
グリスはCPUクーラーに付属する
グリスはCPUに付属のCPUクーラーや別売のクーラーに付属しますので、別途手配は不要です。
使用されている素材によって多少の熱の伝導率が変わりますので、CPUの熱が気になりだしたら後で購入する方向で良いと思います。
2017年1月現在ではインテルから第7世代のデスクトップパソコン向けのCPUが発売されたばかりで、CPUとマザーボードの価格が高騰しています。
折を見て価格が下がったタイミングで各種パーツを購入し、実技編を追記しようと考えています。